経緯
サーバーに興味を持ち、2010年頃から自宅の環境で検証を行うようになりました。
サーバー1台目は、IntelのCore2Duoを搭載した家庭用デスクトップPC。
Windows7にファイルサーバーを導入したのがきっかけでした。
その後、大学の講義でRaspberry Piの存在を知り実際に購入しました。
この機器に搭載されているRaspbianはLinux系OSであり、
次第にDebianやCentOSも扱うようになりました。
この機器に搭載されているRaspbianはLinux系OSであり、
次第にDebianやCentOSも扱うようになりました。

CentOSはRedHat系かつ無償であることから、企業での導入率が高いOSでしたが、
CentOSのサポート終了がアナウンスされました。
したがって、今後は別の製品へ移行する必要があり、親和性を求める場合はRHELが対象となります。
この経緯から、Red Hat Developer Subscriptionの登録を行い、
自宅環境をRHELへ早期移行しました。
CentOSのサポート終了がアナウンスされました。
したがって、今後は別の製品へ移行する必要があり、親和性を求める場合はRHELが対象となります。
この経緯から、Red Hat Developer Subscriptionの登録を行い、
自宅環境をRHELへ早期移行しました。
現在は各種サーバーを構築しており、
企業と同等レベルの機能確保を目指しています。
企業と同等レベルの機能確保を目指しています。

運用環境紹介
環境
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| ルーター | YAMAHA RTX1200 |
| スイッチ | NEC QX-S724EP |
| サーバー | HPE ProLiant DL380 G7 (本番環境) FUJITSU PRIMERGY TX120 S3 (検証環境) |
| ハイパーバイザー | VMware vSphere 6.7 Update 3 |
| 仮想マシン |
Red Hat Enterprise Linux 8 CentOS 7 Debian 11 Windows Server 2016 Windows 10 |
| 共有ストレージ | TrueNAS 12 |
ネットワーク構成概要図
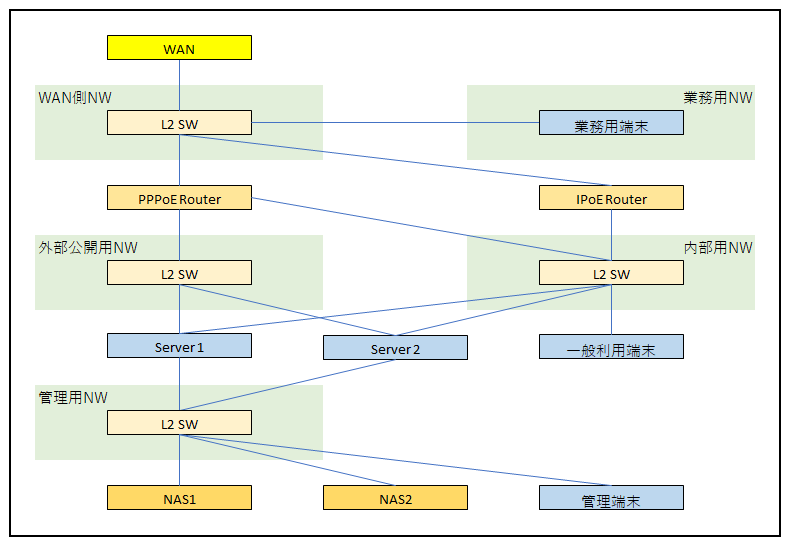
※それぞれのNWは、VLAN機能によって1台のL2スイッチで稼働しています。
■業務環境
プライベートのNW環境と隔離しており、OS標準のPPPoE機能を用いて業務用途プロバイダへ接続しています。
プライベートのNW環境と隔離しており、OS標準のPPPoE機能を用いて業務用途プロバイダへ接続しています。
■プライベート環境
従来のPPPoE接続と、新しいIPoE接続を併用できるように分離しています。
PPPoE接続は外部公開用(ポート開放目的)、IPoEは端末のインターネット閲覧用(速度確保目的)としています。
各サーバーは複数のNICを搭載しており、ハイパーバイザーの仮想スイッチを割り当てています。
VMは用途に応じて、外部公開用または内部用NWに接続しています。
管理用NWにはハイパーバイザー及び、全てのVMが接続されており、RDP・SSHのリモート接続を受け入れます。
バックアップ共有ストレージとして、NASのiSCSI接続機能を提供しています。
管理端末から踏み台サーバー経由でハイパーバイザーにSSH接続を行い、VMのバックアップ処理を行います。
従来のPPPoE接続と、新しいIPoE接続を併用できるように分離しています。
PPPoE接続は外部公開用(ポート開放目的)、IPoEは端末のインターネット閲覧用(速度確保目的)としています。
各サーバーは複数のNICを搭載しており、ハイパーバイザーの仮想スイッチを割り当てています。
VMは用途に応じて、外部公開用または内部用NWに接続しています。
管理用NWにはハイパーバイザー及び、全てのVMが接続されており、RDP・SSHのリモート接続を受け入れます。
バックアップ共有ストレージとして、NASのiSCSI接続機能を提供しています。
管理端末から踏み台サーバー経由でハイパーバイザーにSSH接続を行い、VMのバックアップ処理を行います。
仮想マシン搭載概要図
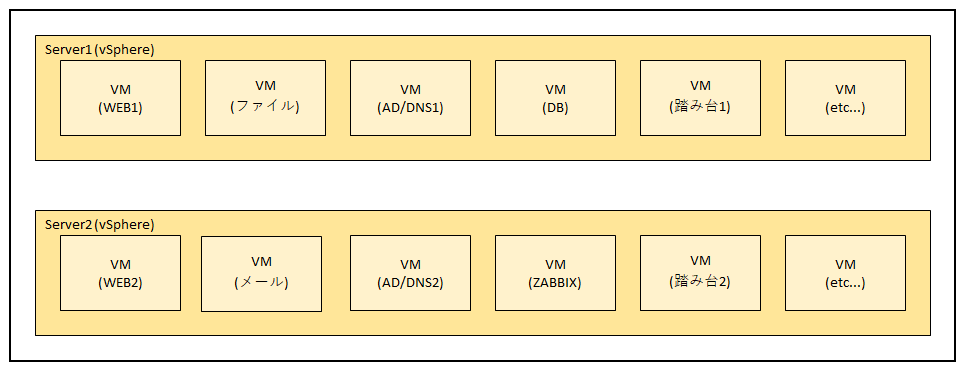
サーバーは2台稼働しています。
稼働サーバー機能は図の通りです。
稼働サーバー機能は図の通りです。
